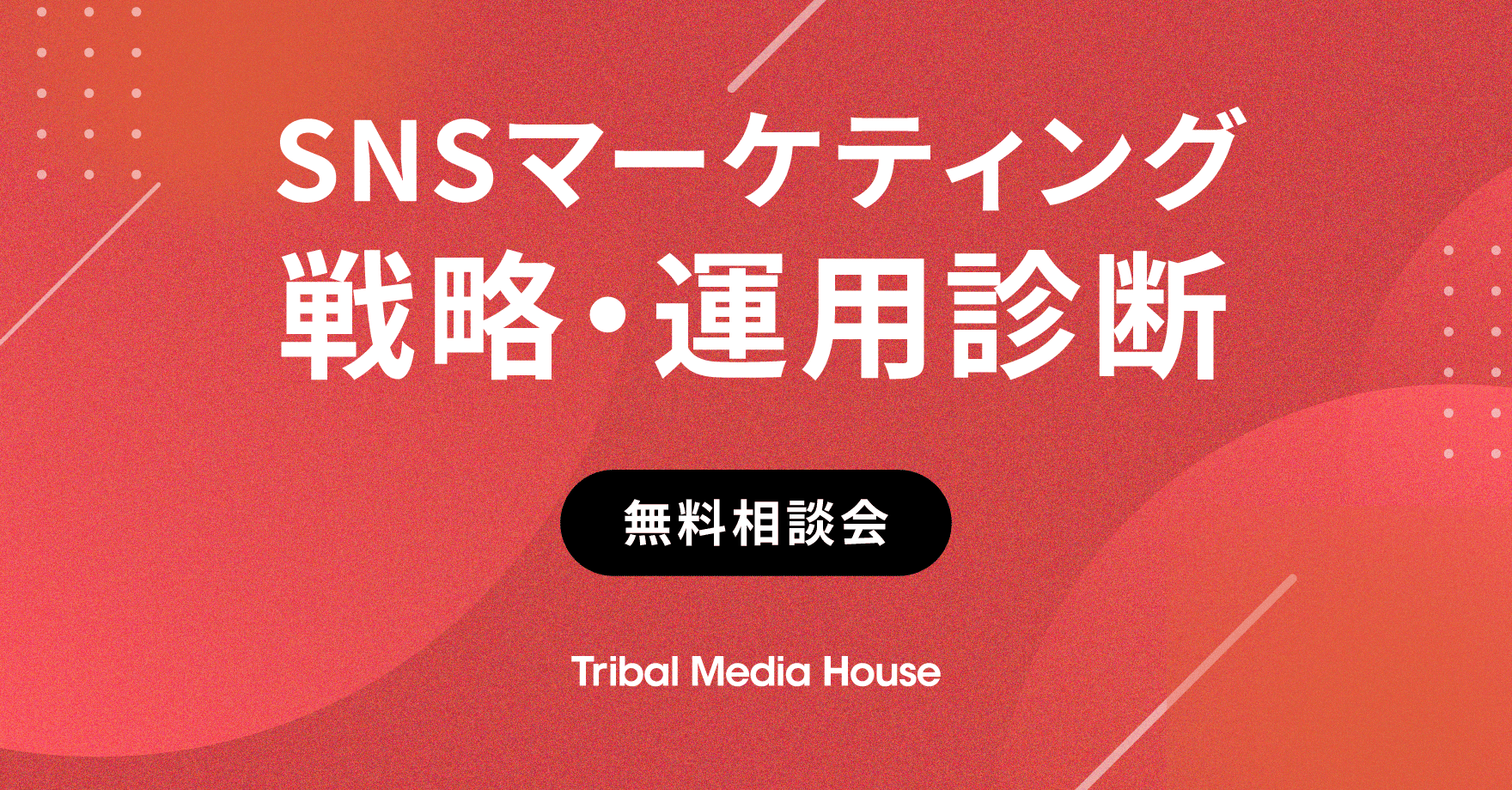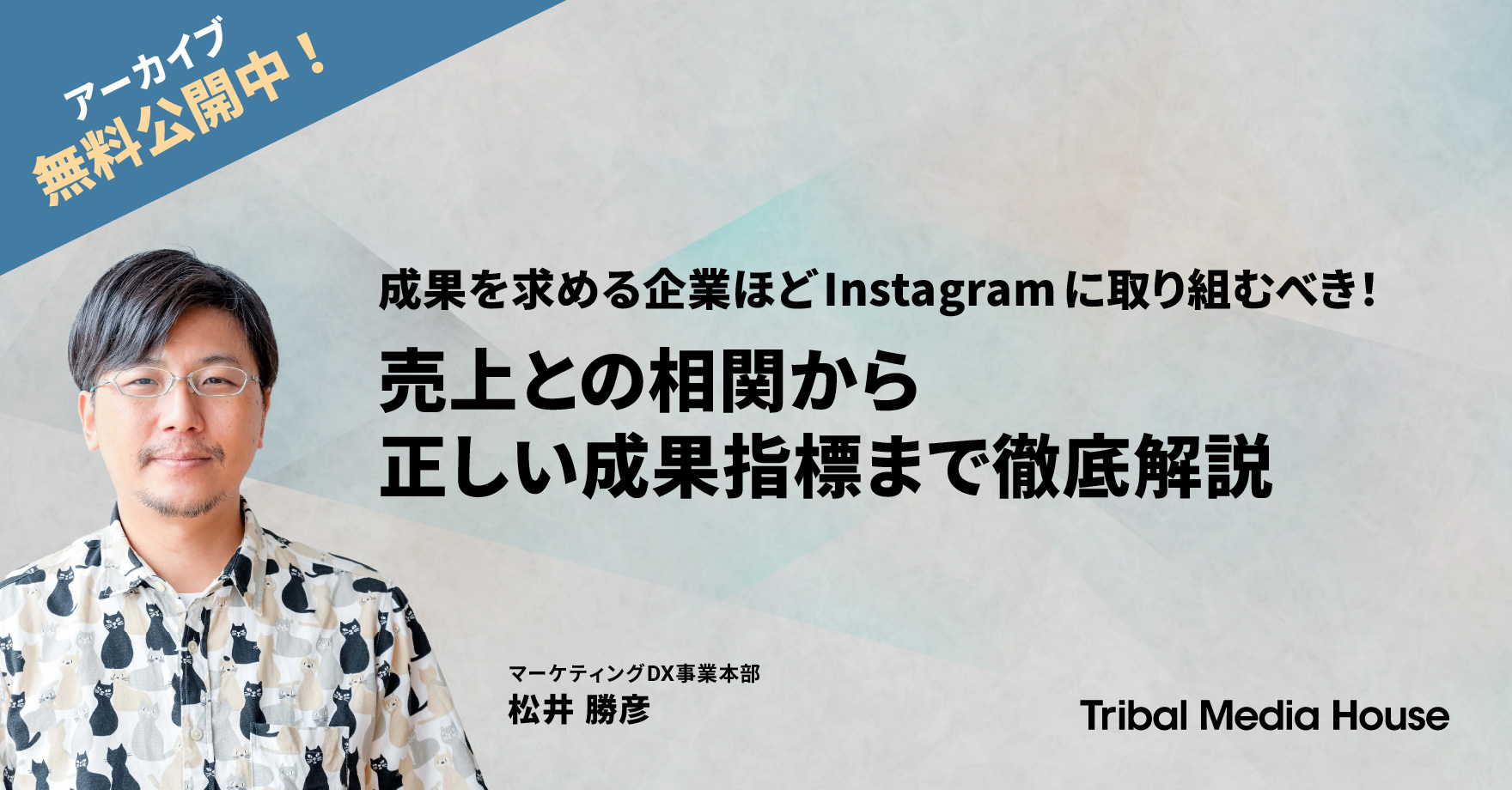インフルエンサーマーケティングとは?やり方や成功事例をご紹介
最終更新日:2025-09-11作成日:2023-03-13
スマートフォンの普及とSNSの普及にともない、消費者の購買行動は大きく変化しました。テレビCMや雑誌広告といった従来のマスメディアの影響力が相対的に低下する一方で、SNS上でフォロワーと強い信頼関係を築く「インフルエンサー」の発信が、消費者の購買判断・意思決定に大きな影響を与えています。
この変化に対応し、多くの企業がマーケティング戦略の一つとして「インフルエンサーマーケティング」に注目しています。
この記事では、インフルエンサーマーケティングの基礎からに取り組むにあたってのメリット、具体的な実践方法や成功事例まで網羅的にご紹介します。
インフルエンサーマーケティングとは?
インフルエンサーマーケティングとは、主にSNS(Instagram・YouTube・TikTok・Xなど)において、特定の分野やコミュニティに対して強い影響力を持つ人物(インフルエンサー)を起用し、その発信力を通じて企業の商品やサービスを宣伝・PRするマーケティング手法です。
消費者は、企業からの一方的な広告よりも、信頼するインフルエンサーからのおすすめやレビューに共感し、購買意欲を高める傾向があります。この消費者心理を活用するのが、インフルエンサーマーケティングの基本的な考え方です。
インフルエンサーマーケティングの市場規模
株式会社サイバー・バズと株式会社デジタルインファクトが実施した「2024年国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向調査」によると、2025年のインフルエンサーマーケティング市場は995億円、前年比116%の規模にまで拡大する見通しです。さらに2029年には、2024年対比で約1.9倍、1,645億円に達すると予測されています。
また、2024年の日本のインフルエンサーマーケティング市場規模のチャネル別内訳は、YouTubeが280億円と最も高く、次いでInstagramが260億円、TikTok(ライブ配信アプリを含む)が175億円、X(ブログを含む)が135億円となっています。
2022年まではTikTokとXのインフルエンサーマーケティングの市場規模は同じ水準でしたが、近年は縦型ショート動画で表現できる幅が増えたり、縦型動画の制作環境が整備されたことをきっかけにニーズが高まり、TikTokの市場規模がXの市場規模を抜きました。
今後はInstagram、YouTube、などの主要なソーシャルメディア含め、縦型ショート動画を使ったインフルエンサーマーケティングの需要が増えると予測されています。
インフルエンサーマーケティングが注目を集める理由
現代においてインフルエンサーマーケティングが重要視される背景には、以下の点があげられます。
SNS利用者の増加と情報収集行動の変化
多くの人が日常的にSNSを利用するようになり、同時に商品やサービスに関する情報をSNS上で検索し、特定の分野に詳しいインフルエンサーの投稿を参考にしたりするようになりました。
広告に対する消費者の態度の変化
生活者の情報リテラシーが高まったことで、従来型の広告だけでは商品・サービスの購買にいたらず、より信頼できる第三者(インフルエンサー)からのレコメンデーションを求める傾向が強まっています。
ターゲティング精度の高さ
特定の趣味嗜好やライフスタイルを持つフォロワー層を抱えるインフルエンサーを起用することで、企業が狙うターゲット層へ効率的にアプローチすることができます。
共感と信頼にもとづいた情報伝達
インフルエンサー自身の言葉や体験を通して語られる情報は、広告特有の宣伝色を感じさせにくく、フォロワーからの共感や信頼を得やすいという特徴があります。
これらの理由から、インフルエンサーマーケティングは、消費者との効果的なコミュニケーションを築くうえで欠かせない手法となっています。
インフルエンサーマーケティングのメリット
インフルエンサーマーケティングには、主に4つのメリットがあげられます。
1.信頼性の向上と高い訴求力の獲得
インフルエンサーのファン(フォロワー)は、そのインフルエンサーに対して高い信頼や好感を抱いているため、インフルエンサーが発信する商品やサービス内容についてもポジティブな印象を持ちやすく、信頼性が高い情報として受け取る傾向にあります。その結果、購買などのアクションにつながりやすくなります。
2.ターゲット層への認知拡大
インフルエンサーはたくさんのフォロワーに対して直接情報を届けることができるので、効率的に広く認知を獲得することができます。
3.消費者目線でのレビュー獲得
インフルエンサーマーケティングでは、インフルエンサーが消費者の視点で商品やサービスのレビューをしてくれるため、フォロワーは商品の特徴をよりクチコミに近い自然な言葉で理解することができます。
4.クチコミ効果(UGC)の誘発
インフルエンサーの投稿がきっかけとなり、そのフォロワーによるさらなるクチコミ(UGC: User Generated Content)が発生し、情報が拡散していく効果も期待できます。ポジティブなクチコミが広がることで、さらに商品やサービスの信頼性が高まります。
SNS時代におけるUGCの重要性については、こちらの記事をご確認ください。
UGC(User Generated Content)は、消費者の信頼を得ながらブランド認知や購買促進につなげる強力なマーケティング手法です。本記事では、UGCの意味やマーケティングにおける重要性、活用のメリットなどを解説します。マーケティング担当者は必見です。
インフルエンサーマーケティング実施の7ステップ
ここからは、インフルエンサーマーケティングの実施方法を以下の7ステップでご紹介します。
1.目的・目標を明確にする
インフルエンサーマーケティングを成功させるには、まず「何を達成したいのか」を明確にすることが大前提です。施策の方向性がぶれないよう、以下のポイントを押さえましょう。
主な目的は「認知の獲得」と「購入・利用意向の向上」の2つです。
| 認知獲得を目的とする場合の目標 | ・リーチ数・インプレッション数 ・エンゲージメント率(いいね数・コメント数・シェア数・保存) ・フォロワー数 ・UGC(ユーザー生成コンテンツ)の投稿数 など |
| 購入・利用意向の向上を目的とする場合の目標 | ・商品名の検索数 ・サイト訪問数(商品ページへのトラフィック) ・クーポン・キャンペーンコードの利用数 ・購買につながるアクションが期待できるコメント内容の数 など |
ここで重要なことは、売上を直接的な目的にしないことです。
インフルエンサーマーケティング施策は、コミュニケーションを通じてフォロワーに「使ってみたい!」「欲しい!」と感じてもらうことが得意であり、実際に商品・サービスが購入されるまでには商品力や価格、店頭のシェア、市場や他社状況、天候などさまざまな要因が影響するためです。
そのほか目標設定とあわせて、以下の点も決めておきましょう。
- 具体的な実施方法
- 実施予算
- 実施時期
- 商品(サービス)と訴求ポイントの設定
- 使用するハッシュタグの設計
- イベントやサンプリングの実施、およびその内容
2.ターゲットの設定
次に、インフルエンサーマーケティングを通じて、誰に情報を届けたいのか、ターゲットとなる顧客層を具体的に設定します。以下の項目について整理されているとよいでしょう。
- 年齢
- 性別
- 居住地
- 興味関心
- 職業
- 普段利用しているSNSプラットフォーム
など
ターゲットを設定する際にはソーシャルリスニングによる現状の分析がおすすめです。
ソーシャルリスニングとは、SNSやQ&Aサイト、ブログなどのソーシャルメディア上の生活者の声(クチコミ、UGC)を収集、分析し、商品企画やサービスの改善などに役立てるマーケティング手法のことです。
ソーシャルリスニングによって実際にどんな人が自社の商品や競合他社の類似商品に対してどのような内容を語っているのかを事前に把握することができ、施策を実施した後にどのくらい効果があったのかを測ることができます。
自社だけで分析をすることが難しい場合は、外部に委託するのもよいでしょう。
ソーシャルリスニングについて詳しく知りたい方は以下の関連記事もご確認ください。
ソーシャルリスニングとは何かを、実施する目的やメリットなどを解説しながらまとめた記事です。具体的な手法やクチコミの収集方法、分析方法、収集したデータを活かすポイント、おすすめのツールなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
3.プラットフォームの選定
ターゲット顧客層がどのSNSプラットフォームを主に利用しているか、また、商品やサービスの特性に合わせて、最適なプラットフォームを選定します。
| 画像や動画が中心。ファッション、美容、グルメ、旅行など、ビジュアル訴求が有効な商材に向いています。ストーリーズやリール、ライブ配信など機能も豊富です。 | |
| YouTube | 商品の詳細なレビューや使い方の解説、専門的な情報の伝達に適しています。幅広い年齢層に利用されています。最近ではショート動画でより手軽に情報を取得しやすくなっています。 |
| TikTok | 短尺動画が中心。若年層に人気が高く、トレンドやエンターテイメント性の高いコンテンツが拡散されやすいです。ダンスやチャレンジ企画などが有効です。 |
| X(旧Twitter) | テキストベースでリアルタイム性、拡散性が高いプラットフォーム。ニュース性の高い情報やキャンペーン告知、ユーザーとのコミュニケーションに向いています。 |
そのほかにFacebook、LINE VOOMなど、商材やターゲットに合わせて検討します。
商品カテゴリーごとにどのプラットフォームで施策を行うべきかお悩みの場合は、こちらの記事も参考にしてください。
各SNSを含むソーシャルメディアやインフルエンサーを活用したマーケティングがどのくらい消費者にとって影響力をもつのかを独自調査をもとに解説します。
4.インフルエンサーの選定
設定した目的、ターゲット、プラットフォームに基づき、最適なインフルエンサーを選定します。株式会社トライバルメディアハウスではインフルエンサーを特性に応じて3つのタイプに分類しております。
パワーインフルエンサー
パワーインフルエンサーは、フォロワー数が多くリーチ力のあることが特徴。知名度のある方を起用することで商品名やブランド名を広く知ってもらうことができます。新商品発売に際し、認知を獲得したい時に起用することを推奨します。
投稿内容は自分主語での日常投稿がメインで、フォロワーは、その人への憧れや期待が強い傾向にあります。幅広いリーチに特化している一方、商品理解やアクションにまでつなげることが難しい場合もあります。
カテゴリーインフルエンサー
カテゴリーインフルエンサーは、料理や家具・家電、アウトドアなど特定カテゴリーへの愛着や探究心が強く、投稿で使用されるクリエイティブのデザインなどが統一され、独自の世界観を持っていることが特徴です。同じ世界感やカテゴリーを好むフォロワーからの信頼性が高く、その方々への影響力が強い傾向にあります。紹介の質が高く、カテゴリーに特化した投稿をしているため、投稿を見たフォロワーもブランドや商品への理解や愛着が深まりやすいです。
ブランドインフルエンサー
ブランドインフルエンサーとは、特定のブランドが好きでそのブランドについて熱量高く投稿するインフルエンサーです。フォロワーもブランドそのものへの関心が高い人が集まりやすいことに加え、ブランドが好きで普段から推奨行動を行っているためフォロワーの意向形成につながりやすい傾向にあります。
インフルエンサーを選定する際はフォロワー数を重視するケースがよくありますが、それだけでは選定したインフルエンサーが自社とどれだけ親和性が高いかがわかりづらい場合があります。インフルエンサーを選ぶ際にはフォロワー数以外にも商品・サービスのターゲット層とインフルエンサーのフォロワー層が一致しているかなども確認しておきましょう。
詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
インフルエンサーマーケティングは目的を正しく設定し、適切な方法でインフルエンサーを選ぶことで、効果的にインフルエンサーとはそもそもどういった人物なのか実施することができます。本記事ではインフルエンサーの定義や特徴、そしてマーケティング活用時の選定ポイントを解説します。
5.インフルエンサーへの依頼
起用したいインフルエンサーが決まり次第、依頼を行います。
依頼方法としては、インフルエンサー本人に直接DMなどで連絡する方法や、所属事務所、キャスティング会社を通じて依頼する方法があります。連絡する内容は以下のような点を押さえて送りましょう。
- イベント内容や商品内容
- 訴求するポイント
- 投稿の要件(投稿日時・投稿文・ハッシュタグ・投稿画像など)
- 宛名や住所(※商品PRの場合)
- 報酬(支払い方法・支払い先)
- 禁止事項
- そのほか(緊急連絡先など)
6.コンテンツの企画と施策の実施
正式にインフルエンサーから快諾を得られれば、コンテンツの企画と施策の実施に取りかかります。
1)インフルエンサーと依頼内容をすり合わせる
用意した案内文、企画書などを用いて、インフルエンサーと依頼内容や投稿内容のすり合わせを行います。インフルエンサーから質問を受けることもあるため、想定される質問や回答などをあらかじめまとめておくとスムーズに対応することができます。
企業側の指示が細かすぎると、フォロワーに響かない広告感のある内容になってしまうため、インフルエンサー側の意見やアイディアを尊重しながら企画しましょう。
2)商品を発送・イベントに招待する
プランニング内容にもとづいて、サンプリング商品を発送したり、イベントに招待したりします。送付商品については、投稿しやすくするためのラッピングや手紙などを用意するのもポイントです。運用時に人員が足りない場合は、外部パートナーなどに依頼することも検討しましょう。
3)投稿の実施と投稿内容を確認する
インフルエンサーによる投稿を契約に含めない場合は、投稿意思はインフルエンサーに任せることとなります。ですが、送付商品への工夫を含めて、できるだけ投稿してもらえるような企画やコミュニケーションをとることは重要です。投稿後は記録や検証のために、投稿やコメントのキャプチャ画像を取るようにしましょう。
7.効果測定と分析
施策実施後には、効果測定をおこないます。主な測定方法は各SNSプラットフォームが持つ分析ツール、ステップ2でご説明したソーシャルリスニング、そしてアンケート調査です。
SNSの分析ツールのデータはインフルエンサーに提供してもらう必要があるため、事前に依頼をしましょう。このデータによってリーチ数やいいね数、インプレッション数、エンゲージメント率などのユーザーのアクションが分析できます。
ソーシャルリスニングでは、クチコミの発生数、クチコミ内容のポジティブ・ネガティブ判定、など定量、定性の両面で測定、分析ができます。
また、中長期的にはフォロワー向けにアンケート調査を実施し、どのような情報がブランドの認知や購買につながったかを分析しましょう。
社内での実施が難しいようでしたら、外部への委託もおすすめします。
インフルエンサーマーケティングの費用対効果の考え方
インフルエンサーマーケティングの費用対効果(ROI)を測ることは、施策の価値を評価し、継続的な改善を行ううえで非常に重要です。
特にインフルエンサーマーケティングではインフルエンサーとの良好な関係を築きながら、中長期的な視点でROIを評価しましょう。
フォロワーによるインフルエンサー投稿への接触というのは、商品・サービスの認知から購入そしてリピートという一連のブランド体験のごく一部であり、接触時間としてはほんの数分です。そのため、短期かつ単発的なインフルエンサーの投稿だけではフォロワーのブランドイメージの定着は難しいです。
そのため、ROIは単純な売上だけでなく、以下のような多角的な視点で評価することが推奨されます。
| 短期的な効果 (リーチ数・インプレッション数の増加) | エンゲージメント率(いいね数・コメント数・シェア数・保存)の向上 フォロワー数の増加 UGC(ユーザー生成コンテンツ)の増加 |
| 中期的な効果 (商品ページへのトラフィック増加) | リード(見込み客)獲得数 クーポン・キャンペーンコードの利用数 商品名の検索数の増加 アクションが期待できるコメント内容の数 |
| 長期的な効果 (ブランド認知度の向上) | ブランドイメージの向上や改善 商品・サービスの直接的な売上 顧客ロイヤルティの向上 |
これらの指標を、事前に設定したKPIと照らし合わせながら評価します。
インフルエンサーマーケティングの事例紹介
ここではインフルエンサーマーケティングの具体的な活用事例を交えながら解説します。株式会社トライバルメディアハウスが関わっている事例とそうでない事例がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社ユニクロ
ユニクロは、人気YouTuberとして活躍する『ヒカキン』と『セイキン』を起用した施策を行いました。『奢り合いバトル』と題したバラエティ企画を通じて、ユニクロの商品をYouTube動画で紹介しています。
P&Gプレステージ合同会社『SK-II』
化粧品ブランド『SK-Ⅱ』では、Instagramのフォロワー数が158万を超え(2023年2月14日時点)、女優や経営者として活躍する紗栄子さん(@saekoofficial)を起用。商品を交えたエイジングについてのInstagram投稿をしています。同ブランドのInstagramアカウント(@skii)の「タグ付けされている人」を見てみると、他にも女優さんやモデルさんを起用していることがわかりますので、あわせてご覧ください。
ベル ジャポン株式会社『キリ』
クリームチーズでおなじみのブランド『キリ』は、Instagramでライフスタイルを発信するインフルエンサー、石岡真実さん(@mami_ishioka)を起用。『おもいっキリご自愛キャンペーン』と題して、商品を使ったご自愛レシピを実際に作りながらライブ配信で紹介しています。
“『キリ』を展開する株式会社ベル ジャポンのインフルエンサー施策、プロモーション事例をご紹介します。Xではクチコミ創出を目的にインフルエンサーの起用とキャンペーンを実施。Instagramではライブ配信や広告出稿を実施しました。結果3.5万件以上のクチコミ創出とブランド認知の拡大に成功しました。”
象印マホービン株式会社
象印マホービンでは、おしゃれなライフスタイルを紹介するインスタグラマーのかやさん(@kaya.log)を起用。Instagramの投稿では、企業や商品についてご自身の地元や幼少期からの思い出とともに紹介し、フォロワーからも同社について語るようなコメントがありました。
株式会社ヤマサキ『ラサーナ 海藻シルキーヘアスプレー』
ヘアケア商品『ラサーナ 海藻シルキーヘアスプレー』では、投稿の強制・指定や金銭的な報酬に基づいた契約を行わないブランドインフルエンサー施策を実施しました。インフルエンサーは商品についての紹介だけではなく、自らの愛用歴やブランドへの愛着を語る内容を投稿。新商品に対する興味喚起・購買意向に成功した事例です。
「ラサーナ 海藻シルキーヘアスプレー」を展開する株式会社ヤマサキのブランディング事例についてご紹介します。Instagramにてインフルエンサーを起用したサンプリング施策を実施。フォロワー(ないし生活者)の新商品に対する興味喚起・購買意向の形成に貢献した
インフルエンサーマーケティング実施の注意点
インフルエンサーマーケティングには、キャスティング以外にも注意しておきたい点があります。ここでは、クリエイティブとインフルエンサーとのコミュニケーションに関する問題と対策について解説します。
投稿コンテンツの品質担保
1つ目は、投稿コンテンツの品質についてです。投稿するのはインフルエンサー自身であるため、表現方法もインフルエンサーに任せた方が広告感がなく自然に伝わる傾向にあります。一方で、企業が期待する内容を発信してもらえるかどうか不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
解決策として、インフルエンサーの普段の投稿の傾向や、起用するインフルエンサーのフォロワーが求める情報を踏まえたうえで、投稿を依頼することが大切です。過去にも企業から依頼された投稿をしている場合は、その投稿内容を把握するだけでなく、通常投稿とタイアップ投稿のエンゲージメント数や率の違いを確認しておくとよいでしょう。
インフルエンサーとの関係構築
インフルエンサーを起用し投稿を依頼したからといって、その企業に好意的でなければ協力的ではない場合もあります。またインフルエンサー自身もその企業を常に好きでいるとは限りません。依頼する際の関係づくりを怠ることで、かえって期待を裏切り、ファンでなくなってしまう可能性も考えられます。
インフルエンサーの起用にあたっては、商品の利用者であれば日頃の感謝の気持ち、提供する商品への想いなどを伝え、単なる仕事の依頼だけではないコミュニケーションをとることが重要です。商品への理解と愛着をさらに深めながら、持続的な関係性を築いていきましょう。
まとめ
インフルエンサーマーケティングについて、メリットや実施のステップ、起用にあたってのポイントまで幅広くご紹介しました。
インフルエンサーマーケティングに取り組むうえでもっとも大切なことは、起用したいインフルエンサーのことを深く理解し、良好な関係性を築くことです。インフルエンサー自身も1人のユーザーであり、ファンであり、お客様の代表であるという意識を忘れないようにしましょう。
インフルエンサーマーケティングに限らず、マーケティングや広報戦略から施策まで、トライバルメディアハウスがお力になれることがあれば、以下よりお問い合わせください。サービス内容のご紹介や具体的なご相談など、お気軽にご連絡ください。
「認知度は高いのに売上につながらない」「施策を実施しても成果が出ない」などのお悩みはありませんか? 経験豊富なコンサルタントが貴社の課題を分析し、最適な解決策をご提案します。 まずはお気軽にお問い合わせください。
関連記事
今回は、インフルエンサーマーケティングにおける「ブランドインフルエンサー」の考え方をご紹介します。「ブランドインフル…
代表の池田(@ikedanoriyuki)が、さまざまなフィールドの第一線で活躍されている方とご飯を食べながらカジュアルに議論する…