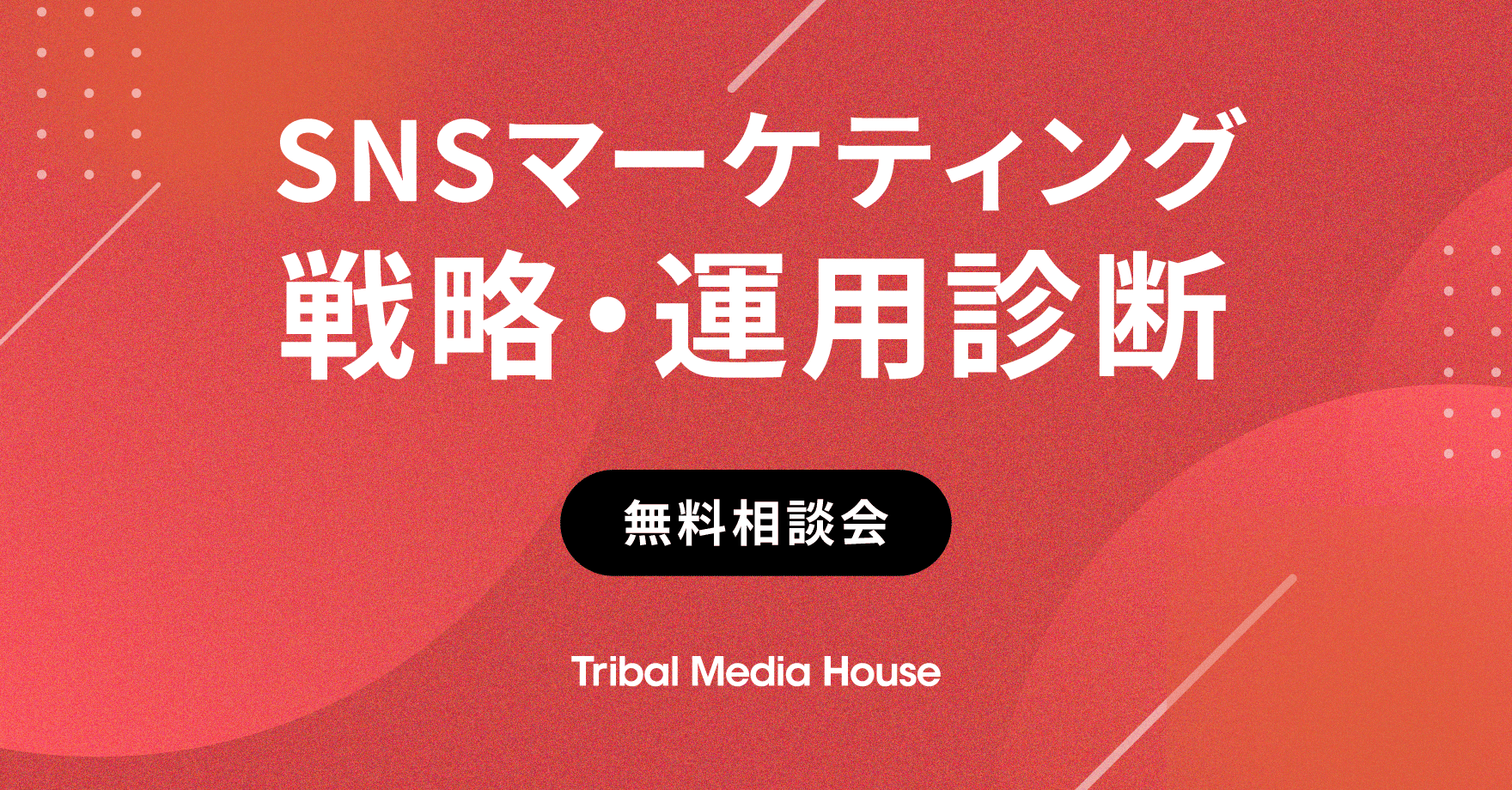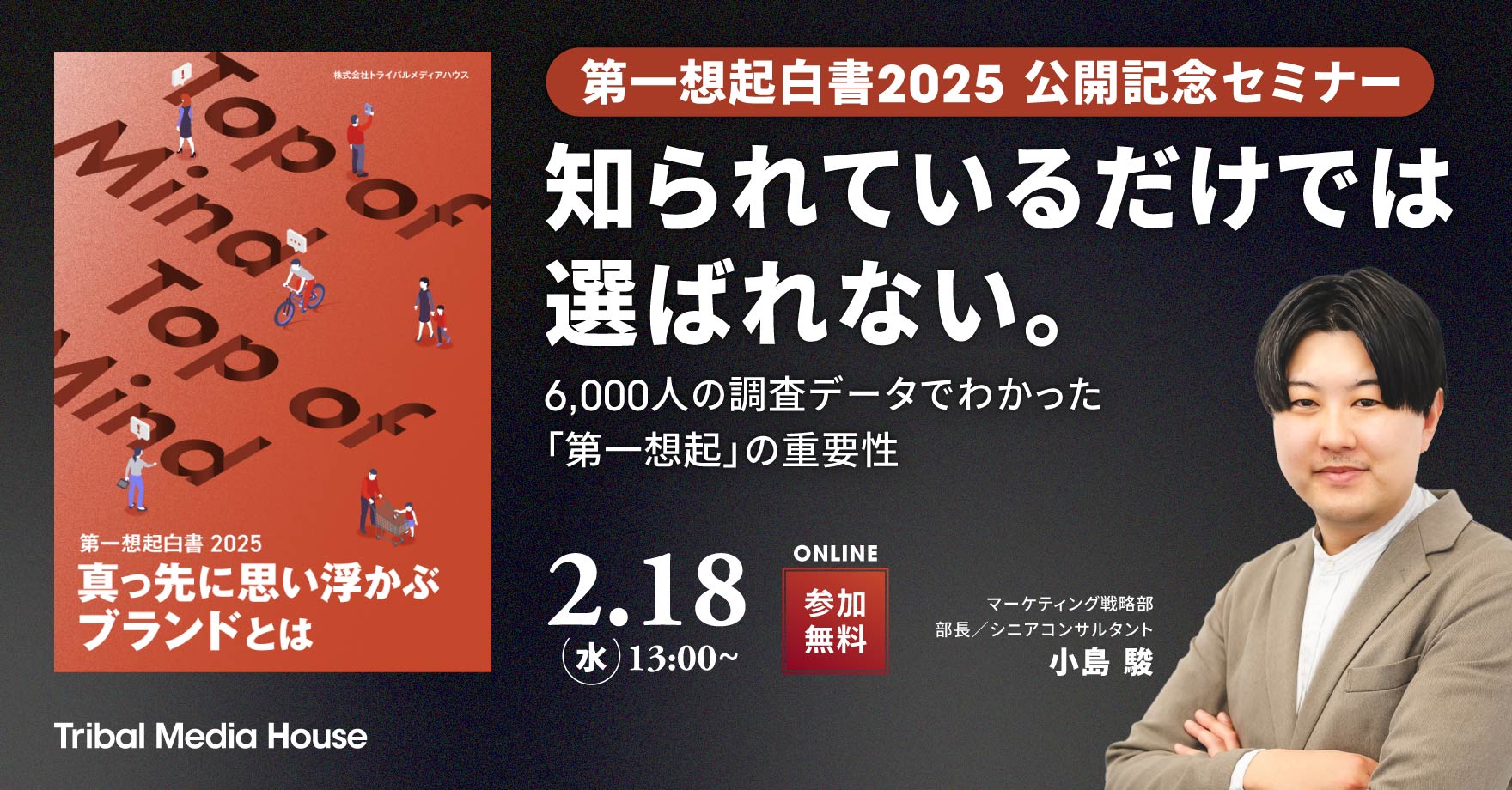企業のXアカウント運用のポイントとは?フェーズごとの施策もご紹介!
最終更新日:2025-07-18作成日:2025-04-25
X(旧Twitter)は、個人の自己表現としての役割だけではなく、企業の営業活動にも役立つツールです。高い拡散効果をうまく活用して運用することで、集客や売上の向上が図れます。
今回の記事では、X運用を成功させるために必要な知識・情報をまとめました。運用初期に欠かせないポイントから、中期以降の戦略設計のヒントまで網羅しています。これからX運用を始める担当者の方や、成果に伸び悩んでいる方は、ぜひご一読ください。
X運用の基礎知識
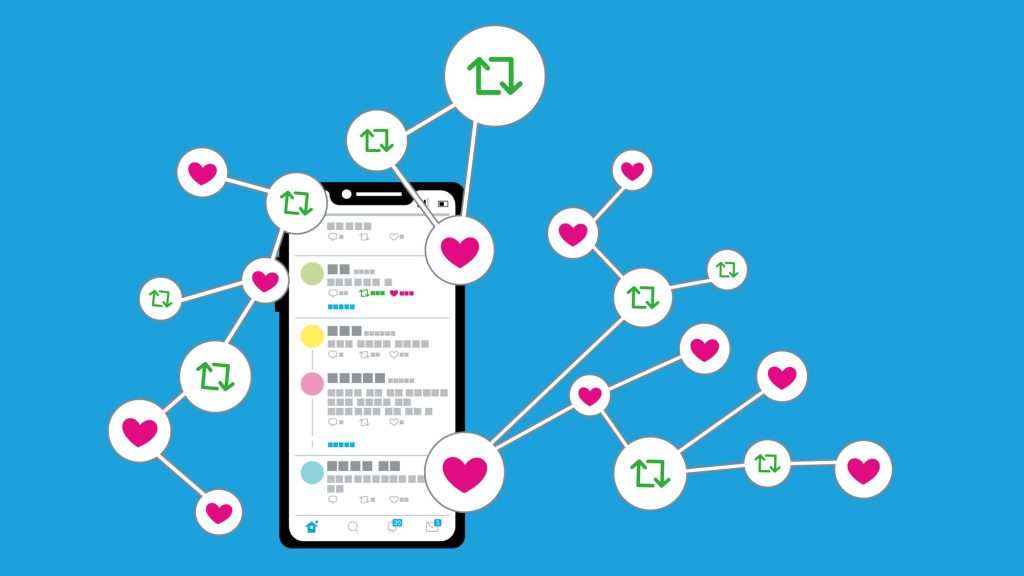
まず、Xの概要と、アプリ内で使用する基本用語について説明します。
Xとは?
Xとは、短文テキストや画像・動画、音声・ビデオ通話による情報発信や双方向のコミュニケーションができるSNSです。基本となる個人向け無料プランのほか、次のようなサービスが展開されています。
- Xビジネス:ビジネス向けアカウント
- Xスペース:音声チャットSNS
- Xプレミアム(旧Twitter Blue):有料会員サービス
- X広告:アプリケーション内で出稿できる広告機能
Xは当初「Twitter」としてリリースされましたが、運営会社の変更にともない、2023年7月に名称がXへ変更されました。
Xの基本用語
Xの基本用語とその機能を紹介します。
| プロフィールページ | アカウント名、自己紹介文、アイコン・ヘッダーなどが設定できるコンテンツ |
| アイコン | アカウントの顔として表示されるプロフィール画像 |
| ヘッダー | プロフィールページの背景画像 |
| ユーザーID | ユーザーの識別番号 |
| 投稿ID | ポストの識別番号 |
| ポスト | 無料版で全角140文字、半角280文字以内の投稿機能 |
| リポスト(RP) | ほかのユーザーのポストを引用・共有すること |
| ミュート | 指定のアカウントのポストを非表示にする機能 |
| ブロック | 指定のアカウントとの相互アクションを制限する機能 |
| タイムライン | ポストやおすすめコンテンツが一覧表示されるページ |
| いいね | 他ユーザーのポストへの好意を表すアクション(ハートのアイコン) |
| フォロー | ポストがタイムラインに配信されるようにする機能 |
| フォロワー | アカウントをフォローしているユーザー |
| ハッシュタグ(#) | 特定のキーワードを識別できるようにする記号 |
上記の用語や機能は、X運用中の頻出ワードとなるため、確実に覚えておきましょう。
企業が公式Xを運用する3つの目的
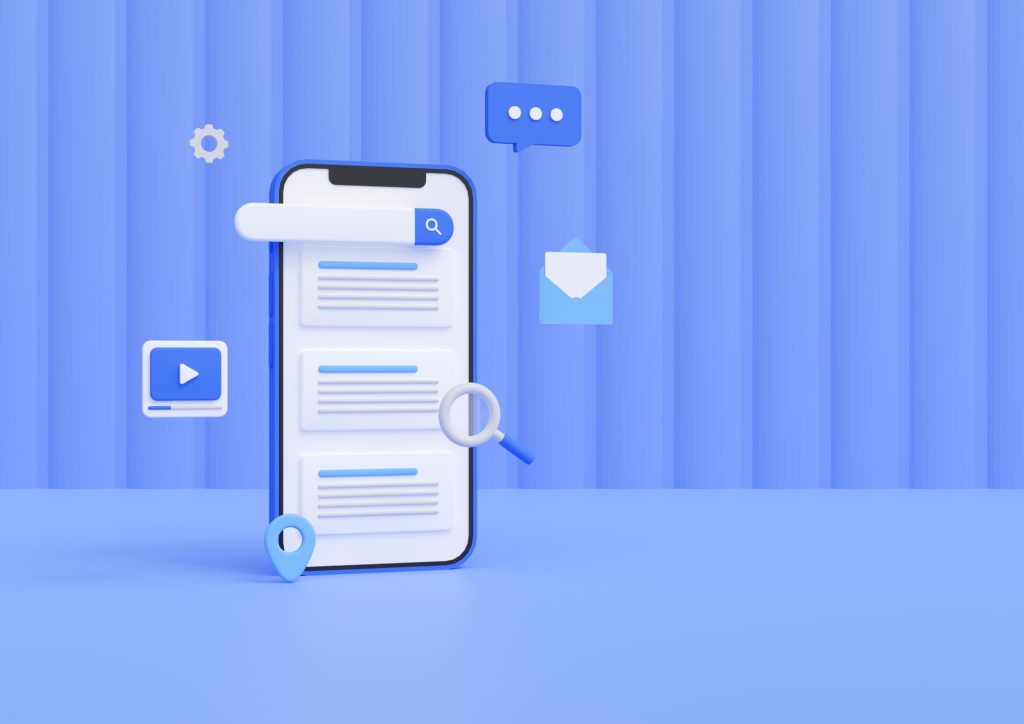
近年、主に次の3点を目的として、多くの企業が公式Xの運用に取り組んでいます。
- 広範囲に情報を拡散する
- たくさんのユーザーと双方向につながる
- 自社資産を形成する
広範囲に情報を拡散する
Xは、極めて高い拡散力を特徴とするソーシャルメディアであり、企業や商品・サービスの認知度向上およびPRに最適です。他ユーザーの投稿をシェアするリポストという機能を通し、情報が波及するように拡散していきます。また、誰でも気軽に投稿できる特性から、UGC(一般ユーザーが生成したコンテンツ)が活発であり、それを活用したマーケティング施策の展開も期待できるでしょう。
たくさんのユーザーと双方向につながる
Xは、企業の営業活動において、ユーザーとのつながりづくりに最適です。Xの2024年第2四半期におけるMAU(月間アクティブユーザー数)は全世界で5億7,000万人。国内では2023年時点で6,700万人に到達しており、既存顧客はもちろん、多くの見込み顧客や潜在顧客にアプローチできる可能性を秘めたツールです。また、日本人Xユーザーの平均年齢は37歳であり、若年層から現役世代まで幅広い利用者を抱えていることも、企業にとって大きな魅力だといえます。
出典:
X広告媒体資料 2024年4〜6月期|X Business
「X Corp. Japan株式会社」への社名変更のお知らせ|X
自社資産を形成する
Xを通して得た膨大なユーザーデータは、貴重な情報資産です。さらに、時間をかけて作り上げたXのコンテンツそのものも自社資産になります。広告といった一時的な宣伝効果ではなく、ストック型の施策なので、運用を継続するほどデータやファンを増やし続けられるという強みがあります。
X運用で重要な7つの指標
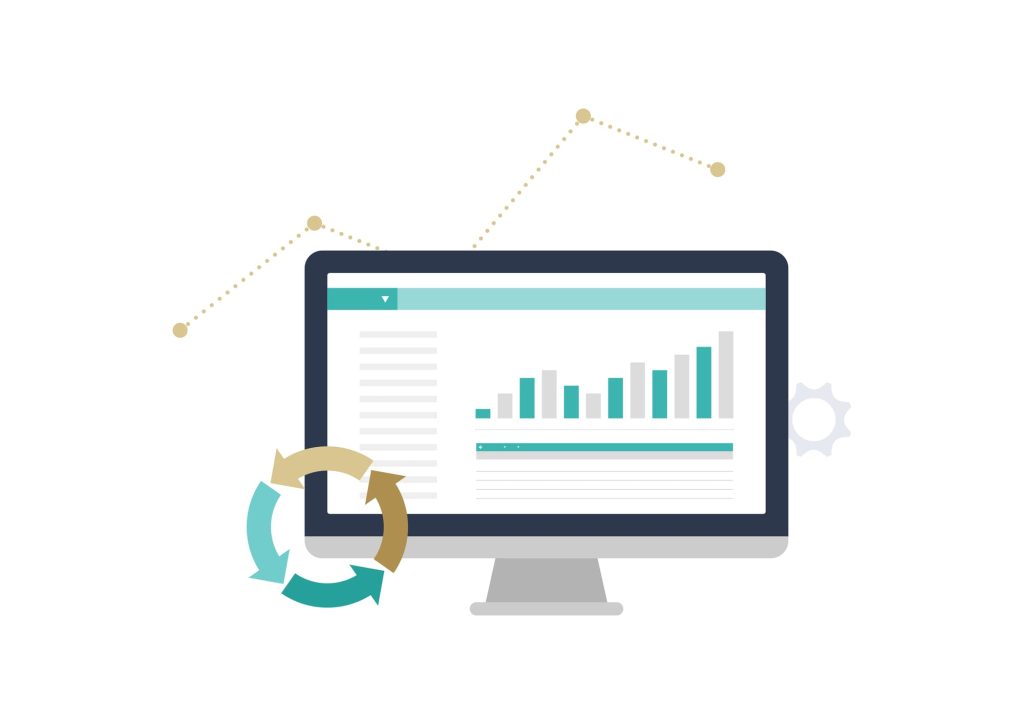
Xには、7つの重要な指標が存在します。インサイト機能を使って計測できる指標もあり、運用効果の分析と戦略・施策の改善に活用できるデータなので、必ず押さえておきましょう。
インプレッション数
Xのインプレッション数とは、自社のポストがユーザーのタイムラインに表示された回数です。いいねやリポストなどのユーザーアクションが、アルゴリズムの判断基準となっているといわれています。ほかの指標とも深い関わりを持ち、運用開始後はインプレッション数を増やすことが第一目標となるでしょう。
プロフィールアクセス率
プロフィールアクセス率とは、インプレッション数のうち、プロフィールにアクセスしたユーザーの割合を示す指標であり、次の計算式で算出できます。
なお、プロフィールアクセス率の平均値は1〜3%程度、理想値は3〜5%です。プロフィールアクセス数が増えるほど、フォロワーが増える可能性が高まります。
フォロー率
フォロー率とは、自社アカウントのプロフィールへのアクセス数のうち、フォローしたユーザーの割合を表す指標であり、計算方法は以下のとおりです。
Xにおける一般的なフォロー率は1〜3%程度なので、運用の際はそれ以上の数値を目指すこととなるでしょう。
エンゲージメント率
エンゲージメント率とは、自社のポストに何らかのアクションを起こしたユーザーの割合です。自社の投稿に対する関心度を表す指標であり、以下の計算式で求められます。
目標となるエンゲージメント率はフォロワー数によって異なりますが、一般的には3〜5%程度が平均です。エンゲージメント率が高いと、商品・サービスの販売促進および売上アップにつながります。
CTR
XにおけるCTRとは、インプレッション数のうち、添付したリンクがクリックされた割合です。別名「クリック率」や「クリックスルー率」などとも呼ばれ、以下の計算式で表されます。
企業の認知度向上や商品・サービスの販売促進、広告の効果を評価する際は、CTRを基準にするとよいでしょう。
KGI
KGIとは「Key Goal Indicator」の略語であり「経営目標達成指標」と訳されるマーケティング用語です。いわゆる戦略における最終目標のことであり、売上や利益率、制約件数など定量的に測れる数値がKGIに設定されるケースが多い傾向にあります。
KPI
KPIとは「Key Performance Indicator」の略語であり、日本語訳では「重要業績評価指標」といいます。簡単にいうと、最終目標であるKGI達成のための中間目標です。KPIには、一般的にインプレッション数やリード数、クリック数など数値で測れる定量的な指標が設定されます。
企業がXを運用する際の注意点

Xにはたくさんのメリットがある反面、留意すべきポイントも存在します。ここでは、企業がXを運用する際の注意点をみていきましょう。
成果が得られるまでに時間がかかる
X運用を開始したからといって、すぐ成果が得られるわけではありません。一般的な有料広告といったマーケティング施策とは異なり、運用を継続して実績を積み上げていくことで、徐々に効果が出てきます。そのため、中長期的な視点で戦略と予算を立てることが大切です。
クレームや炎上のリスクが高まる
Xは、直に会話するより気軽に発言しやすい双方向のコミュニケーションツールなので、運用を始めるとこれまでよりクレームが増える恐れがあります。拡散力が高いことから、自社の投稿が思わぬことで炎上してしまうリスクも否めません。とはいえ、Xを活用する将来的なメリットは、リスクを考慮しても十分な価値があります。健全な運用のノウハウを学ぶとともに、スピーディーなトラブルシュート体制の整備を整備しておきましょう。
X運用を始めるときに押さえておくべき5つのポイント

Xの効果を最大限に高めるには、次の5つのポイントを押さえて運用することをおすすめします。
- 運用の目標を設定する
- ターゲットを絞り込む
- 専門の担当者を決める
- プロフィールページを充実させる
- 定期的に効果を測定する
運用の目標を設定する
公式Xを開設するときは、まずどのような目標を達成したいのかを具体的に定めておきましょう。目標設定によって、運用の方針や方向性が変わります。また最終目標であるKGIだけではなく、中間目標となるKPIを細かく設定しておくことで、途中経過の評価・分析や改善がしやすくなるはずです。
ターゲットを絞り込む
X運用の際は、あらかじめ自社のメインターゲットとなるユーザー層を明らかにしてください。ターゲットの価値観や行動がコンテンツの内容・施策を決定する指針となるため、事前に明確化することで戦略設計がスムーズになります。
専門の担当者を決める
X運用とは、ただアカウントを開設し、投稿していくことを指すのではありません。トレンドのリサーチや広告の運用、データ分析などやるべき施策がたくさんあり、それらをうまく組み合わせた戦略を設計することが必要です。チェック体制を強化してトラブルを未然に防ぐためにも、2人以上の運用担当者を任命することが推奨されます。また担当者の人数が増えると、メンバー間の連携強化が重要となるため、運用の方針やコンセプトの共有の徹底が不可欠です。
プロフィールページを充実させる
Xに公式アカウントを開設したら、プロフィールページを充実させ、どのようなアカウントなのか一目で分かるようにしておきましょう。プロフィールページはアカウントの顔や名刺のようなものであり、それを基にフォローするかどうか判断するユーザーも多いからです。プロフィールページに長文を詰め込むと視認性が落ちるため、シンプルな単語の羅列やリスト表示、外部リンク設置などで簡潔にまとめましょう。
定期的に効果を測定する
Twitterはただ運用を続ければよいのではなく、数カ月に1回は効果を測定し、その結果を活かして運用体制を改善していくことが必要です。また効果測定には、各種数値の集計やフォロワーの反応、メッセージやクチコミの内容など、詳細なリサーチと正確な分析が求められます。
SNSマーケティングにおける分析のやり方を徹底解説。おすすめの無料・有料ツールや分析レポートの活用術をお伝えします。正確な分析結果に基づく戦略設計・改善でPDCAサイクルを回し、運用の最適化を測りましょう。
X運用の初期に有効な手法

公式Xのアカウントを開設した後は、段階を踏んで戦略的に施策を展開していくことで、運用を最適化していくことが可能です。ここからは、X運用をスタートしたばかりの初期に有効な施策を解説します。
トレンドキーワードを盛り込む
トレンドキーワードをテキストに含めたり、ハッシュタグをつけたりしてポストを投稿することで、多くのユーザーのタイムラインに表示されやすくなります。運用初期ではいかにインプレッションを増やせるかが課題となるため、トレンドキーワードを積極的に盛り込んで投稿を作成しましょう。
画像や動画を添付する
Xは短文投稿が基本となりますが、画像や動画と組み合わせることで、視認性の高いコンテンツが作れます。画像や動画はテキストより情報量が多く、意図が伝わりやすくなるため、積極的に活用しましょう。ただし、Xの規約違反やセンシティブな内容に該当する画像・動画を投稿すると、削除やアカウントロックのリスクがあるので注意してください。
利用率の高いタイミングを見計らって投稿する
自社アカウントのポストを多くのユーザーに閲覧してもらうためには、ターゲット層の利用率が高いタイミングを見計らって投稿することが重要です。なお、一般的にSNSの利用率が高いのは次の3つのタイミングだといわれています。
- 通勤時(7〜9時、17〜19時)
- 昼休み(12〜13時)
- 夕食後・就寝前(20〜22時)
ただし、上記はあくまでも目安であり、ターゲット層の年齢やライフスタイルによって適切なタイミングが異なります。特に、閲覧にある程度の時間がかかるコンテンツを投稿する際は、ターゲット層がゆっくり閲覧できる時間帯を狙って投稿すれば、閲覧率が高まるでしょう。
ユーザーのニーズを満たす情報を配信する
企業がXを運用するときは、ユーザーのニーズを把握し、興味・関心を引く内容を投稿するよう心がけてください。商品・サービスの宣伝はポスト全体の2〜3割程度に留めるのが理想だといわれており、それ以上はくどい印象を与えかねません。製品の活用のヒントや開発の裏話といったユーザーの役に立つ情報を積極的に発信することで、エンゲージメントが高まり、多くのファンが獲得できます。
ユーザーとの交流を増やす
Xを通し、たくさんのユーザーと双方向に交流することで、結びつきが強まり、共感や好感度、満足度の向上につながります。自社商品・サービスに関するポストや本文に自社アカウント名が含まれる@ポストに返信・リポストしたり、フォローバックしたりなど、交流の機会を積極的につくってみてください。
X運用の中期以降に実践すべきマーケティング施策

X運用に慣れてきたら、さらに一歩踏み込んだ戦略を設計しましょう。以下では、運用の中期以降に効果的なマーケティング施策を紹介します。
固定ポストを設置する
投稿数がある程度増えてきたら、固定ポストを設置しましょう。固定ポストとは、自社アカウントのタイムラインに特定の投稿を常時トップ表示させる機能のことであり、ポストがピン留めしたように表示されます。
固定ポストは、自社のタイムラインにアクセスしたユーザーの目に最初に触れる投稿なので、アカウントのイメージを決定づける重要な要素です。名刺代わりとなるポストを固定するほか、新商品の発売やキャンペーンに合わせて変えていくなど、いま最もみてもらいたい情報を効果的にアピールできます。
広告を出稿する
X運用の集客効果をさらに高めたいときは、X広告の出稿・運用がおすすめです。通常のポストと同様に、返信やリポストなどのアクションが可能であり、拡散されれば大きな宣伝効果が生まれます。最低金額が設定されていないので、低予算でも気軽に運用できるのが強みです。
また、X広告では、目的や課題に応じて選べる独自のキャンペーンも展開されています。認知度向上、ユーザーのアクション促進、コンバージョン率アップなど、課題に応じてピンポイントの対策が可能です。
さらにX広告を通して得たデータを利用して分析を深めれば、運用成果の分析も可能であり、戦略や施策を最適化していけるでしょう。
キャンペーンを実施する
Xにおけるキャンペーンとは、懸賞の一種です。アカウントをフォローしたり、指定した内容をポスト・タグ付けしたりしたユーザーへ、商品や特典を進呈します。見返りの大きい企画は多くのユーザーの参加が募れるため、エンゲージメント率の向上につながるでしょう。
ただし、Xでキャンペーンを実施するときは、ルールに沿って進めなければなりません。たとえば、実施のために複数のアカウントを作成したり、同じ内容を繰り返しポストさせたりなどの行為は禁止です。
また、キャンペーンは参加者が集まりやすい一方で、効果が一時的なものになりやすい傾向にあります。キャンペーンをきっかけに、ほかの投稿にも興味を持ってもらえるよう、内容を充実させていくことが必要です。
ウェブサイトカードを活用する
ウェブサイトカードとは、ポストのアイキャッチとなるリンク付きの画像や動画を設置できる広告クリエイティブです。活用することでデザイン性や視認性が高まるため、Xから任意のWebサイトやページへ誘導したいときに有効な手法だといえます。
なお、ウェブサイトカードには、写真や画像を設置する「画像ウェブサイトカード」と、動画の「ビデオウェブサイトカード」の2種類があります。広告用アカウントだけではなく、通常のポストにも設置できるので、見込み顧客へアプローチに効果的です。
インフルエンサーマーケティングを実践する
インフルエンサーマーケティングとは、多くのフォロワーを抱える人気のアカウントやユーザーを起用し、商品・サービスを宣伝してもらうマーケティング施策です。特定の分野・領域で強い影響力を持つインフルエンサーの力を借りることで、認知度が一気に高まるほか、たくさんの反応やアクションが期待できます。
フォロワーの信頼を得ているインフルエンサーによる投稿は、企業が自社商品を宣伝・PRするときのような、わざとらしい印象を与えにくいのもメリットです。自社のイメージや商品・サービスへの関連性が高いインフルエンサーを起用して、売上アップにつなげましょう。
トラブル対応の体制を整備する
運用を始めてしばらく経つと、どれほど慎重を期していても、トラブルやクレームが発生しやすくなります。対応を誤ると、トラブルの悪化や炎上の原因になるため、事前に体制を整えておくことが肝心です。
事前に、社内でトラブルやクレームへの対応マニュアルやチェックリストを作成し、担当者や従業員に共有しておきましょう。また、対応窓口を設置し、万が一のときでもすみやかに対応できる体制を整えることも必要です。スムーズな対応をみせれば、トラブルが最小限に抑えられるほか、逆に印象アップにつながるかもしれません。
SNS運用にあたって、企業が押さえておくべき社内・社外ルールの策定について徹底解説。ガイドラインの作成方法や、策定する際の注意点も紹介します。運用方針のマニュアル化がまだ済んでいない方は、ぜひ参考にしてください。
X運用でよくある失敗事例

よくある失敗事例を分析すれば、リスク回避と成功のコツがみえてきます。ここからは、X運用でついやりがちなミスから、最適化のポイントを探っていきましょう。
イメージやコンセプトにズレが生じる
これまでのイメージからズレた情報や内容を投稿してしまうと、フォロワーが減少するリスクが高まります。既存フォロワーは現在のコンセプトに共感しているユーザーであり、方向性が突然変わると混乱を招きかねません。一度決めた運用目的やイメージ、コンセプトは基本的に変えないほうがよいため、策定の際は慎重に検討してください。
誘導テキストを過度に使用する
誘導テキストの過度な使用はユーザーに好まれず、フォロワー離脱の原因になります。また、ポストの肝心な部分や結論をあえて述べず、リンクへ誘導する手法はもう古く、逆効果になりかねません。リンクの過度な設置は避け、特典を用意するなど、+αの付加価値のある導線づくりが有効です。
自社がフォローするアカウントの数を増やしすぎる
むやみにフォロー数を増やしすぎると、タイムラインやフィードが雑多な投稿で埋まってしまうほか、スパムだと判断されるなどの弊害が生じます。自社アカウントのフォロワー数に対するフォロー数の適切な比率は、1〜5割以内です。フォロー数を増やし、ユーザーと積極的に交流すること自体は決して悪い行為ではないため、節度を守ったアクションを心がけましょう。
ポストをチャットボットに任せる
チャットボットとは、AIを利用した会話の自動生成プログラムです。SNSと連動すれば投稿の自動化も可能ですが、機械的で単調な内容になりやすいため、使用は極力避けるほうがよいでしょう。親しみや温かみが感じられるポストを投稿し続けることで、自社アカウントや投稿に興味を抱くユーザーが増えていくはずです。
企業の公式Xアカウントを成功させたいなら運用サービスを利用しよう
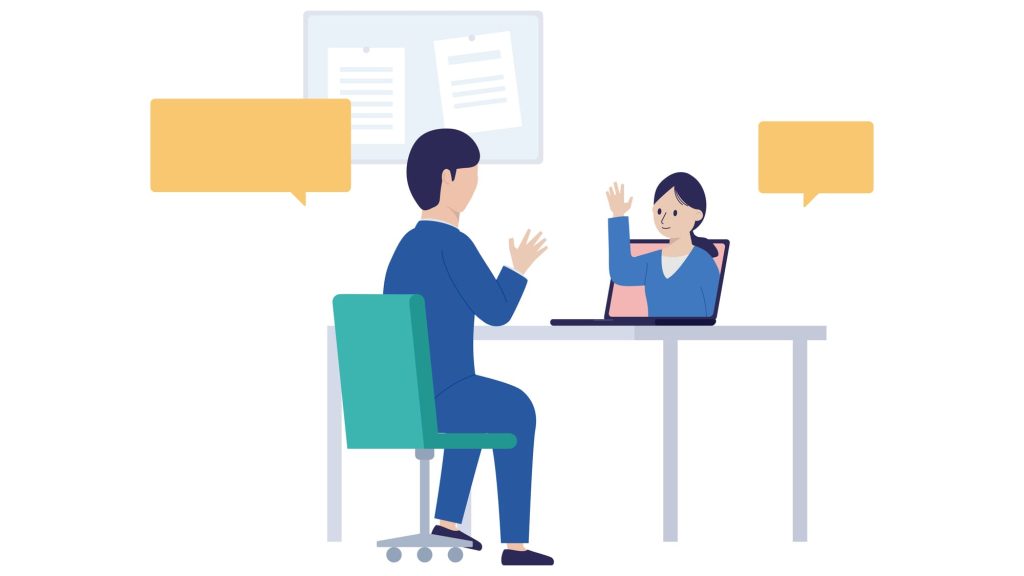
ここまで説明してきたように、企業の公式Xを効果的に運用するには、プラットフォームの特性に対する深い理解と的確な戦略設計が不可欠です。運用を始めたばかりで、リソースがないという企業も多いでしょう。X運用を最適化する近道は、プロの知恵を借りることです。ここからは、X運用サービスの特徴と費用相場を紹介します。
X運用・代行サービスとは
X運用・代行とは、戦略設計やポストの作成・投稿、効果測定・分析などを支援するコンサルティングサービスです。業界・業種や企業の特性やトレンドを踏まえ、最適な戦略を立案して運用を最適化します。
X運用をプロに任せるメリット
X運用のプロの協力を仰ぐことで、自社リソースの有無にかかわらず、初期から効果的な運用が可能です。
Xは気軽に始められる反面、売上につなげるには専門的な知識が必要な分野も少なくありません、実践からノウハウを身につけたり、これから勉強を始めたりするのは、タイムパフォーマンスが悪く、コア業務へ割くリソースを圧迫します。
X運用サービスを利用すれば、コツや最新トレンドを押さえた運用が手軽に実現するため、即時性が求められるX運用における大きな強みとなるでしょう。
X運用の委託にかかる費用
X運用の委託にかかる費用はサービスやプランによって異なるものの、一般的には約10万〜100万円が相場です。ポスト作成のみといったシンプルな業務の代行なら10万円前後で依頼できますが、フル運用や効果測定・分析まで含めると数十万〜100万円程度かかることもあります。
ただし、基本料金の安さだけで選んだ場合、カバーする範囲が狭く、オプションを追加していくうち費用がかさむケースもあるので注意してください。自社の課題とプランの内容、会社の実績や専門性を照らし合わせ、コストパフォーマンスのよいサービスを選ぶことが大切です。
X運用のご相談は「トライバルメディアハウス」へ
X運用を最適化するには、確かな知識・ノウハウに基づく戦略設計が不可欠です。運用の段階に応じてさまざまな施策を組み合わせることで、明日の売上につながります。
「これからX運用を始める」「思うような成果が出ない」といった悩みを抱えていましたら、「トライバルメディアハウス」へご相談ください。「X(旧Twitter)運用」サービスで、中長期的に効果の出せる体制構築や戦略設計を支援します。具体的な要件や目的が定っていなくても、現在のリソースや課題に合わせて最適なプランを提案しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
Xの特性を踏まえた施策を、戦略立案から実施、効果測定まで行います。
「認知度は高いのに売上につながらない」「施策を実施しても成果が出ない」などのお悩みはありませんか? 経験豊富なコンサルタントが貴社の課題を分析し、最適な解決策をご提案します。 まずはお気軽にお問い合わせください。